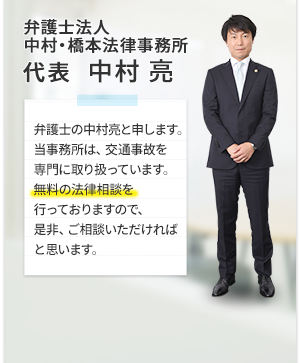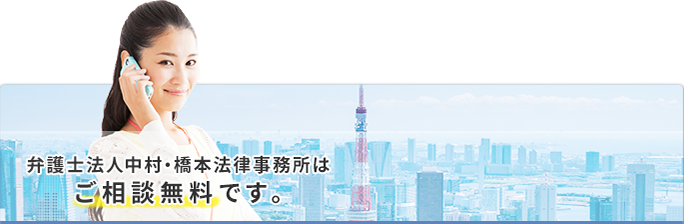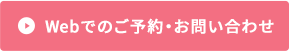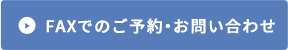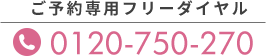70 事故当時91歳の男性被害者の死亡慰謝料について、保険会社提示の1000万円から、2.4倍の2400万円へ増額した事案。
死亡事故 :死亡事故 、90代男性
死亡
事故当時91歳の男性被害者の死亡慰謝料について、保険会社提示額2.4倍へ増額した事案です。

 2,850
2,850
| 保険会社提示額 | 1,600 万円 |
| 増加額 | 1,250 万円 |
交通事故状況
被害者は、自転車に乗り道路を横断しようとしたところ、左方から進行してきた四輪車に衝突され、骨盤骨骨折等の傷害を負い、出血性ショックによりお亡くなりになりました。
ご依頼者のご要望
被害者の相続人の方が、保険会社から損害賠償金の提示を受けており、提示された金額が妥当かどうか確認したいとして、ご相談に来られました。
受任から解決まで
提示された金額を確認すると、損害賠償金として、約1600万円と提示されていました。
このうち、特に、慰謝料(被害者本人分及び近親者分の合計金額)は、1000万円と提示されており、裁判基準と比較して大きな差がありました。
そこで、当事務所にて受任後、訴訟を提起し、裁判基準による解決を目指しました。
その結果、慰謝料を2400万円(被害者本人分として2200万円、近親者分として相続人1名につき100万円)とし、今後支払額2850万円にて、裁判上の和解により解決しました(被害者の過失割合は、基本過失割合20%です。)。
死亡慰謝料、近親者慰謝料
交通事故の被害者が死亡した場合、被害者のほか、近親者も加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。
被害者の損害賠償請求権は民法第709条もしくは自動車損害賠償保障法第3条に基づくものですが、近親者の損害賠償請求権は民法第711条に基づいており、根拠となる条文が異なります。
さて、自賠責保険は、死亡による損害に関して、被害者本人の慰謝料として350万円、遺族の慰謝料として、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円と定めています。
本件では、被害者の相続人が2人であったことから、保険会社は、当初、被害者本人の慰謝料として350万円、遺族の慰謝料として650万円の合計1000万円を提示していました。
しかし、赤い本は、被害者が死亡した場合の慰謝料について、「一家の支柱2800万円、母親・配偶者2400万円、その他2000万円~2200万円」としており、自賠責保険が定める被害者本人の慰謝料の金額と比較しても、大きな差があります。
そのため、自賠責保険基準にて示談することは、妥当ではありません。
ところで、赤い本は、「本基準は死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者の分も含まれている。」と記載しており、保険会社は、当該記載を根拠として、被害者本人分と近親者分を合計した金額として、赤い本記載の金額を主張することが多く見受けられます。
本件でも、訴訟提起後、加害者は、慰謝料について、被害者本人分と近親者分を合計して2000万円と主張しており、前述した赤い本の記載を念頭に置いていると思われます。
しかし、仮に、このような主張を前提とすると、相続人の有無及び人数に応じて、被害者本人の慰謝料の金額が異なることとなりかねません。
当事務所では、死亡事故に関しては、常に、被害者本人分の慰謝料のほか、近親者分の慰謝料も請求しており、本件でも、最終的に、被害者本人の慰謝料として2200万円、近親者の慰謝料として相続人1名につき100万円とし、合計2400万円が認定されました。
このように、保険会社は、ご遺族の方に対しては、自賠責保険基準により慰謝料を算出して損害賠償額を提示することが多いですが、裁判基準と比較しても大きな差があります。
もし、保険会社から提示された賠償金額が妥当かどうかご不安のある方がおられましたら、示談をされる前に、一度、弁護士にご相談されることをお勧め致します。


事故当時91歳の男性被害者の死亡慰謝料について、保険会社提示の1000万円から、被害者本人分として2200万円、近親者分として相続人1名につき100万円とし、合計2400万円へ増額しました。
解決事例 関連記事
死亡事故 事例一覧
- 106 事故当時79歳主婦の逸失利益について、年齢別平均ではなく全年齢平均が基礎収入と認定された事案
- 70 事故当時91歳の男性被害者の死亡慰謝料について、保険会社提示の1000万円から、2.4倍の2400万円へ増額した事案。
- 71 事故当時84歳兼業主婦の被害者について、主婦の逸失利益を否定する保険会社に対し、主婦の逸失利益約700万円、最終支払額3400万円にて解決した事案。
- 75 86歳女性被害者の死亡事故について、保険会社提示の示談金約1500万円から、最終支払額2900万円に増額した事案。
- 87 被告は自らに過失はないとして事故の責任を否定していたものの、今後支払額2500万円とする訴訟上の和解が成立した事案。


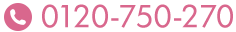
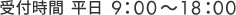






 閉じる
閉じる
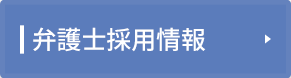
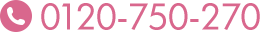


 解決までの流れ
解決までの流れ 解決事例
解決事例 費用について
費用について 交通事故の基礎知識
交通事故の基礎知識 お客様の声
お客様の声 弁護士紹介
弁護士紹介 コラム
コラム