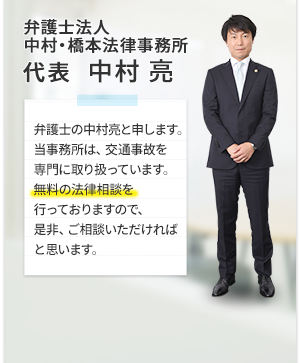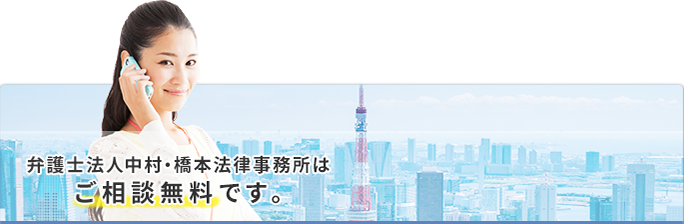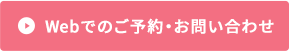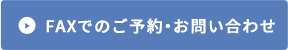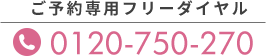74 第10級11号が認定された男子大学生の被害者について、約3400万円にて解決した事案。
後遺障害等級10級11号 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 脛骨・腓骨骨折 、16歳(事故当時)、男性、大学生
右足関節の機能障害
第10級11号が認定された男子大学生の被害者について、約3400万円にて解決した事案です。

 3,400
3,400
| 保険会社提示額 | - 万円 |
| 増加額 | - 万円 |
交通事故状況
被害者は、原動機付き自転車を運転して青信号に従い交差点を直進したところ、対向方向より青信号に従い右折してきた四輪車に衝突され、右下腿両骨骨折等の傷害を負いました。
基本過失割合は、被害者15%、相手方85%です。
ご依頼者のご要望
被害者の方は、治療中にご相談に来られ、右足関節に機能障害が残存していたこと等から、後遺障害として適切な認定を受けること等をご希望されていました。
受任から解決まで
当事務所にて受任後、当事務所のスタッフが、被害者の通院に同行しました。
そして、後遺障害診断書の作成に際して、足関節の可動域を記入して頂くに当たり、医師が適切に可動域を測定しているかどうかを、実際に測定に立会って確認するなどのサポートを実施しました。
その後、被害者請求により後遺障害の申請をし、右足関節の機能障害として第10級11号が認定されたため、裁判基準にて損害額を積算し、賠償交渉を開始しました。
保険会社は、当初、労働能力喪失率を第11級相当の20%として逸失利益を算出しましたが、賠償交渉を続けた結果、労働能力喪失率を第10級相当の27%として逸失利益を算出し、最終的に、約3400万円にて、任意交渉により解決しました。
下肢の機能障害
後遺障害の認定基準では、下肢の障害として、欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害が定められています。
このうち、機能障害とは、3大関節(股関節・膝関節・足関節)の動きの障害のことを言い、障害の程度、また、障害が両下肢に生じたか、一方の下肢に生じたかにより、等級が異なります。
実務上、よく見受けられる等級として、第12級7号、第10級11号があります。
第12級7号は、患側の関節可動域が健側の関節可動域の3/4以下に制限される場合に認められ、例えば、右足関節の可動域が左足関節の可動域と比較して3/4以下しか動かない場合がこれに当たります。
また、第10級11号は、患側の関節可動域が健側の関節可動域の1/2以下に制限される場合に認められ、同様に、右足関節の可動域が左足関節の可動域と比較して1/2以下しか動かない場合がこれに当たります。
関節可動域は、原則として、他動運動により測定され、例外として、神経麻痺が生じている場合など他動運動によることが相当でない場合には、自動運動により測定されます。
また、機能障害が認定されるためには、関節の動きが制限される原因となる「器質的損傷」が必要となります。
そのため、疼痛により関節の可動域に制限が残存する場合には、機能障害ではなく、神経症状として認められることとなります。
本件では、被害者は、右下腿両骨骨折の傷害を負い、右腓腹筋内部に瘢痕状の拘縮が認められたことから、自賠責保険は、「右腓腹筋内部に一部、瘢痕状の拘縮あり。MRIにおいても一部変性が認められる。」とする後遺障害診断書上の診断結果をそのまま認定した上で、被害者の足関節について、患側が背屈5度・底屈30度の合計35度であったのに対して、健側が背屈60度・底屈75度の合計135度であり、健側の可動域の1/2以下に制限されていることから、第10級11号に該当すると認定しました。
このように、機能障害の認定に当たっては、器質的損傷が認められることはもちろんですが、それ以上に、可動域がどの程度であるのかが重要となります。
しかし、中には、残念ながら、後遺障害診断書上、医師が正確に可動域を計測せず、目測による凡その数値が記載されていたり、神経麻痺ではないにもかかわらず、自動値のみが記入され、他動値が記入されていないなど、本来であれば後遺障害が認定される程度の可動域制限が残存しているにもかかわらず、そのままの記載内容にて後遺障害の申請をしたのでは、非該当と判断される可能性が高い事案も決して少なくありません。
そのため、当事務所では、事案に応じて、当事務所のスタッフが、被害者の通院に同行し、実際に可動域の測定に立会い、適切に計測が実施されているかを確認するなどのサポートを行っております。
もし、後遺障害の認定にご不安のある方がおられましたら、一度、当事務所までご相談下さい。


大きな争点となった労働能力喪失率について、後遺障害等級の認定通り、第10級相当の27%と認定されました。
解決事例 関連記事
脛骨・腓骨骨折 事例一覧
- 48 左足関節の機能障害、受任前の相手方保険会社の提示はなく、今後支払額約750万円で解決した事案
- 51 後遺障害第14級9号の被害者について、保険会社提示額約80万円から、約5倍の約420万円へ増額した事案
- 58 下肢の短縮障害等を残した主婦について、67歳までの労働能力喪失期間が認められた事案
- 74 第10級11号が認定された男子大学生の被害者について、約3400万円にて解決した事案。
- 96 被害者の過失割合について、基本15%のところ、5%で解決
- 92 事前認定により第14級9号が認定されていた男性会社員について、異議申立てにより併合第11級が認定され、約2200万円にて解決した事案


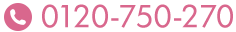
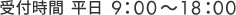






 閉じる
閉じる
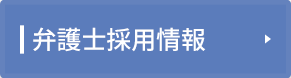
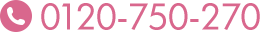


 解決までの流れ
解決までの流れ 解決事例
解決事例 費用について
費用について 交通事故の基礎知識
交通事故の基礎知識 お客様の声
お客様の声 弁護士紹介
弁護士紹介 コラム
コラム