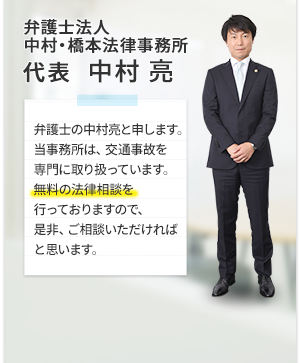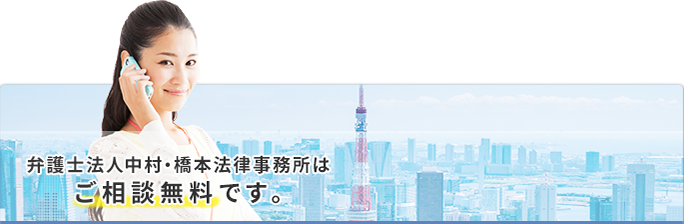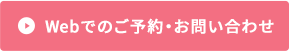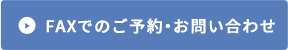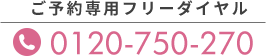48 左足関節の機能障害、受任前の相手方保険会社の提示はなく、今後支払額約750万円で解決した事案
後遺障害等級後遺障害別等級12級~13級7号 :下肢(股、膝、足首、足指)の障害 / 脛骨・腓骨骨折 、40代男性、介護職員
左足関節の機能障害
左足関節の機能障害、受任前の相手方保険会社の提示はなく、今後支払額約750万円で解決
した交通事故事案です。

 750
750
| 保険会社提示額 | - 万円 |
| 増加額 | - 万円 |
交通事故状況
交差点内を歩行中、右折車両に衝突されました(左足関節内果骨折)。
ご依頼者のご要望
後遺障害の異議申立て、相手方保険会社との賠償交渉を依頼したいとのご相談を受けました。
受任から解決まで
被害者の方は、事前認定手続により、自賠責保険上の後遺障害に該当しない(これを「非該当」と言います。)と判断されていました。
そこで、当事務所にて受任後、異議申立てを行い、第12級7号の認定を受けた後、相手方保険会社に賠償請求を行いました。
示談交渉
受任前の相手方保険会社の提示はありませんでした。
当事務所にて賠償請求を行った後、相手方保険会社は、当初、今後支払額約480万円を提示していました。その後、弁護士が賠償交渉を行い、今後支払額約750万円に増額することができました。
異議申立て
後遺障害の認定結果に対して不服があるときには、異議申立てを行うことができます。
今回のケースでは、被害者の方が当初取付けた後遺障害診断書によれば、足関節の可動域について、右(健側/他動):底屈45°、背屈5°、左(患側/他動):底屈45°、背屈0°と記載されており、患側の関節可動域が健側の関節可動域と比較して4分の3以下に制限されていないことから(45°÷50°=90%)、事前認定手続において、非該当との判断を受けていました。
しかし、当事務所にて後遺障害診断書の記載を精査すると、右足関節の背屈の可動域について、他動値が5°であるのに対して、自動値が15°と記載されており、自動値が他動値を上回っていました。
自動値が他動値を上回ることは通常考え難く、これが誤記であることは明らかです。
このように、症状固定の診断に際して、関節可動域が正確に計測されない、もしくは、正確に計測されたとしても、数値の記入に誤りがある場合が時々見受けられます。
このような場合には、正確な関節可動域の数値を後遺障害診断書に記入してもらう必要があります。
そこで、今回のケースでも、被害者の方から受任後、右足関節の背屈の他動値を5°から15°へと修正し、その上で、異議申立てを行いました。その結果、患側の関節可動域が健側の関節可動域と比較して4分の3以下に制限されることから(45°÷60°=75%)、非該当の判断が覆り、第12級7号が認定されました。
機能障害が後遺障害として認定されるためには、後遺障害診断書上の関節可動域の数値が最も重要です。
仮に、数値に誤記があると、本来であれば後遺障害として認定されるべき被害者の方でも、非該当の判断となってしまうことがあります。
後遺障害の認定結果に不服がある被害者の方がおられましたら、異議申立ての可否等について検討させて頂きますので、是非、当事務所までご相談下さい。


異議申立てをしたことにより、第12級7号が認定されました。
解決事例 関連記事
脛骨・腓骨骨折 事例一覧
- 48 左足関節の機能障害、受任前の相手方保険会社の提示はなく、今後支払額約750万円で解決した事案
- 51 後遺障害第14級9号の被害者について、保険会社提示額約80万円から、約5倍の約420万円へ増額した事案
- 58 下肢の短縮障害等を残した主婦について、67歳までの労働能力喪失期間が認められた事案
- 74 第10級11号が認定された男子大学生の被害者について、約3400万円にて解決した事案。
- 96 被害者の過失割合について、基本15%のところ、5%で解決
- 92 事前認定により第14級9号が認定されていた男性会社員について、異議申立てにより併合第11級が認定され、約2200万円にて解決した事案


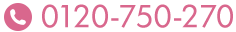
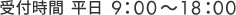






 閉じる
閉じる
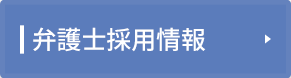
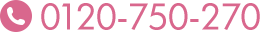


 解決までの流れ
解決までの流れ 解決事例
解決事例 費用について
費用について 交通事故の基礎知識
交通事故の基礎知識 お客様の声
お客様の声 弁護士紹介
弁護士紹介 コラム
コラム